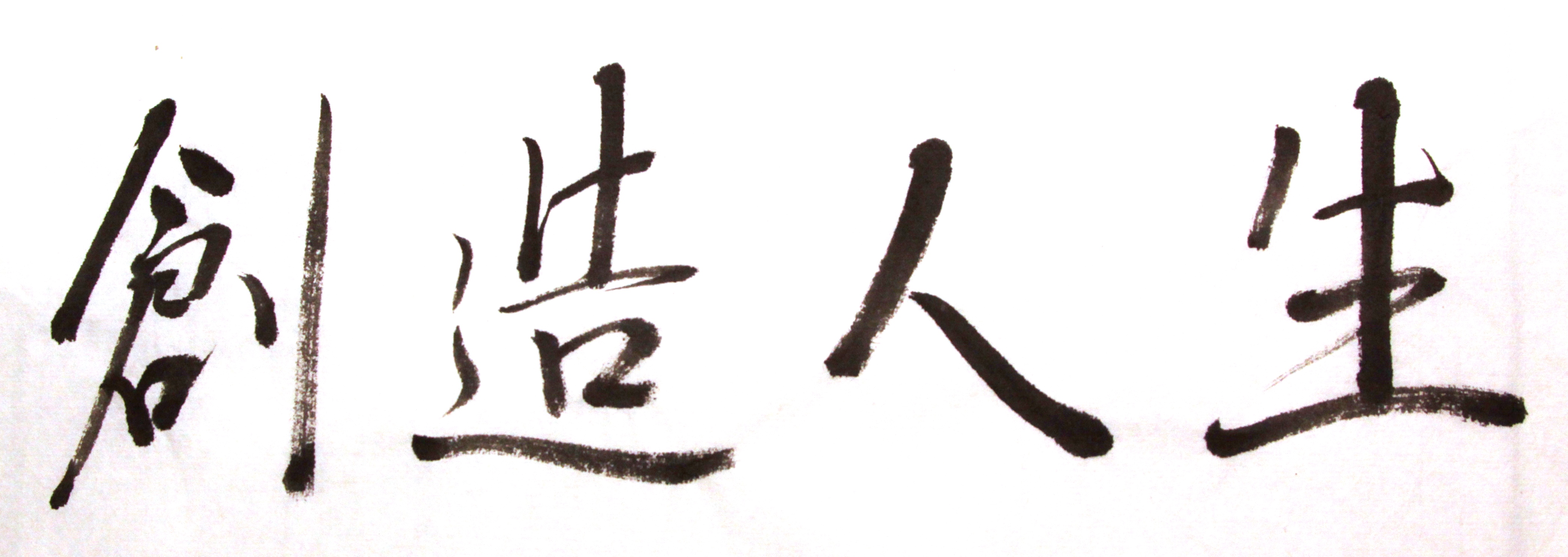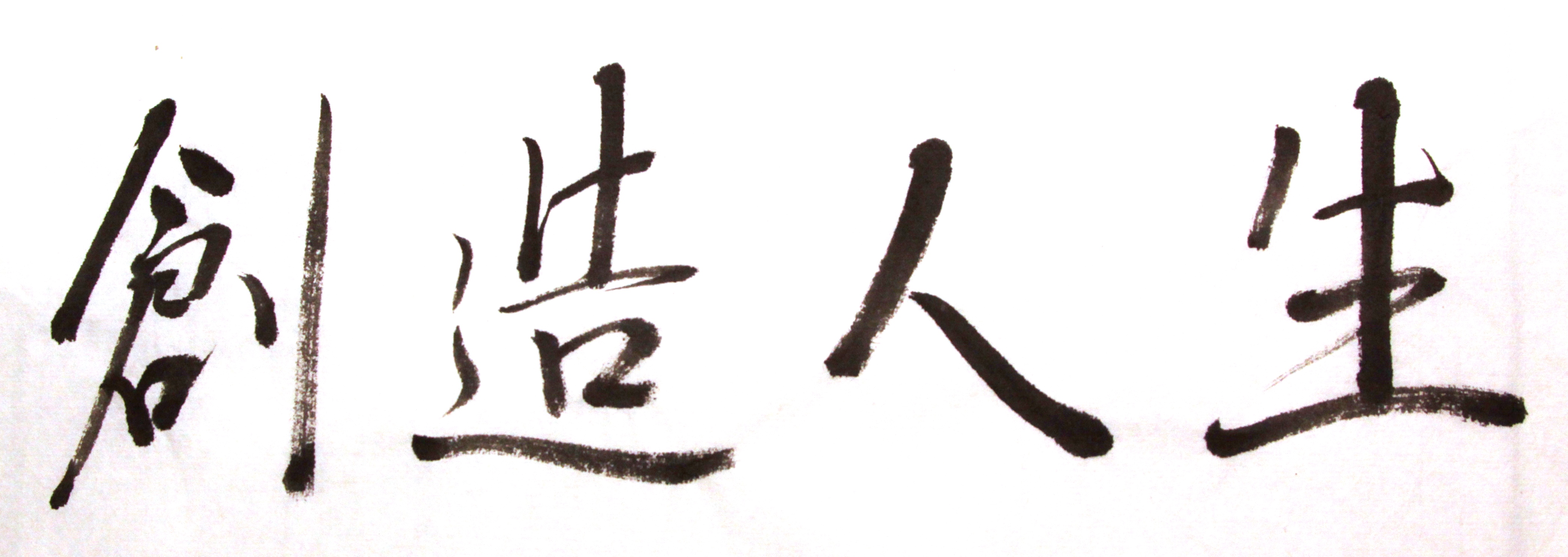「不登校」の原因を知るための3つの方法 「不登校」の原因を知るための3つの方法
不登校などのリスクを克服し明るい前向きな学校生活を目指す小学生・中学生を持つ親子: |
長年、不登校や引きこもりの子供や青年の立ち直りを支援してきた団体の方々は、「少しでも早く、不登校の問題に真剣に向き合うことが重要だ」と指摘しています。真剣に向き合うためにどのような対応が必要かについては、支援者によってそれぞれのやり方がありますが、勿論、単に叱るだけでは逆効果なことが多く、子供のつらさの原因を理解し、信頼を構築することから始めることが重要という点は共通しています。 |
 「創造家族」は不登校の原因を幼児期に遡り見つける 「創造家族」は不登校の原因を幼児期に遡り見つける
不登校などのリスクを克服しポジティブな学校生活を目指す小学生・中学生のお子様とご両親: |
「創造人生」は、幼児期からの生活史に基づき「不登校」の背景要因を見つける |
 不登校の解決法を3つの先進事例から学ぶ 不登校の解決法を3つの先進事例から学ぶ
不登校などのリスクを克服しポジティブな学校生活を目指す小学生・中学生のお子様とご両親: |
様々な対応策を先進事例から学ぶ |
 「創造家族」は、親子で子供が好きなこと・楽しむことを探す一歩から始める 「創造家族」は、親子で子供が好きなこと・楽しむことを探す一歩から始める
不登校などのリスクを克服しポジティブな学校生活を目指す小学生・中学生を持つ親子: |
不登校の裏には、自分が真にやりたいことが見つけられていないことがある |
 個人の多様性と主体性を完全に認めるフリースクールとはどのようなものか? 個人の多様性と主体性を完全に認めるフリースクールとはどのようなものか?
不登校などのリスクを克服しポジティブな学校生活を目指す小学生・中学生・高校生および両親の方: |
既存の教育観を全く変えるアプローチ |
 不登校から自己の独自の価値観を確立した人たち 不登校から自己の独自の価値観を確立した人たち
不登校などのリスクを克服しポジティブな学校生活を目指す小学生・中学生・高校生および両親の方: |
不登校になる人は心が弱い人なのか? |
 親の適切な対応が不登校脱出に最も重要 親の適切な対応が不登校脱出に最も重要
不登校などのリスクを克服しポジティブな学校生活を目指す小学生・中学生・高校生および両親の方: |
親子関係が最も大きい背景要因 |
 「引きこもり」を克服する最大の強みは、自分が真にやりたいことを発見し、自己のアイデンティティーを見つけること 「引きこもり」を克服する最大の強みは、自分が真にやりたいことを発見し、自己のアイデンティティーを見つけること
ひきこもりなどの青年期・ミドルの悩みに対し自分の個性に合った進路を見つけたい方へ: |
青年期に自己のアイデンティティーを獲得した人は、少ない |
 「創造企業」は、「うつ」を跳ね返すため、働き方と職場環境を見直します 「創造企業」は、「うつ」を跳ね返すため、働き方と職場環境を見直します
「うつ」を跳ね返すため、自分の働き方を変え、職場の環境を整えたい方: |
「不安定・うつ」は若者世代で大きく増加 |
 「創造世代」は若年無業者になるリスクを低減し、内発的動機付けを高めプラスに転じるプログラムです。 「創造世代」は若年無業者になるリスクを低減し、内発的動機付けを高めプラスに転じるプログラムです。
若年無業者の経験をプラスに転じ自分の個性に合った進路を探している青年からミドル(15-49歳)の方へ: |
若者世代で若年無業者が急増している |
 仲間遊びが苦手の子のリスクを克服し、才能をプラスに転じる 仲間遊びが苦手の子のリスクを克服し、才能をプラスに転じる
仲間と遊ぶのが苦手の幼児を持つ母親・父親の方: |
仲間遊び苦手の子が持つリスクをポテンシャル |
 子育て不安は何故増え続けているのか? 子育て不安は何故増え続けているのか?
赤ちゃんや幼児の子育てに不安を感じている母親・父親の方: |
ビッグデータ解析によりエビデンスを創る |
 青年期・壮年期の最大の課題は自己のアイデンティティーを見つけること 青年期・壮年期の最大の課題は自己のアイデンティティーを見つけること
一生の選択として自分が真にやりたい職業を見つけようとしている青年からミドル(15-49歳)の方へ: |
青年期に自己のアイデンティティーを獲得した人は、少ない |